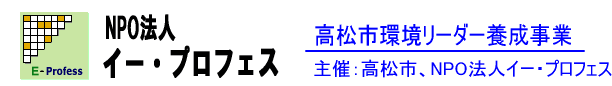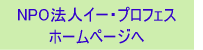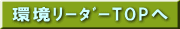※このページでは、講師や関係者に研修内容などについてインタビューした内容を掲載しています
「活動ツール体験習得」の講師担当の香川県地球温暖化防止活動推進センター様に研修内容などについてお伺いしました。
活動ツール体験習得研修においては、環境リーダー候補生に、実際に活動をする際に役立つツールを体験習得してもらうことで、来年度以降の活動に利用できるツールネタの習得を目的としています。
講師プロフィール

香川県地球温暖化防止活動推進センターは、
財団法人香川県環境保全公社が、「地球温暖化対策の推進に
関する法律」に基づき、香川県知事から平成19年6月29日付
で指定されました。
センターの主な事業内容としては、
・温暖化防止に関する広報・啓発活動、
・温暖化防止活動推進員に対する活動支援・研修、
・温暖化防止に関し、地域で活動する団体等への情報提供
などを行っています。
実際の研修は、同センターの福家様、黒岡様、高崎様が
進めていきます。
香川県地球温暖化防止活動推進センターのホームページはこちら

Q1:活動ツール体験習得研修ということですが、「活動ツール」とは何なのでしょうか?
A: ツールとは、道具のことです。
従って、活動ツールというのは、「活動道具」、すなわち「活動をする際に使用する道具」という意味になります。
といっても、これではわかりにくいと思いますので、具体的にイメージしてもらうために、講義(講演)と比較してみます。
まず、講義系の研修はメリットもたくさんあるのですが、一方でむろんデメリットも存在します。
一番のデメリットは、「説明系の研修」ということではないでしょうか。つまり頭で理解する形式なので、興味がない人にとっては面白くない時間となる可能性があります。
一方、活動ツールを用いた研修の特徴は、
・体験、体感
・面白く・楽しく学べる
・自然と啓発ができる
といったところが挙げられます。
受講生に実際に作業に参加してもらい、身体を動かし、頭を働かせて学びます。

Q2:具体的にどのようなツール(環境保全活動をする上でのツール)があるのでしょうか?
A:いろいろあるのですが、昨年の環境リーダー研修で実際やったものを1つ紹介します。
「エネルギーかばん」という活動ツールがあります。
このツールは、生活の中で使用するエネルギー(電気、ガス、ガソリン etc.)を石油の重さに置き換え、日本のかばんの重さを持って体感してみて、他国と比べてみてどうなのかを考えるものです。
諸外国と比べると結構重たい日本のかばんなのですが(つまりエネルギーをたくさん使っている)、その重さを減らすにはどうすればよいか、ムダはどこにあるのかを、参加者の自分自身の生活を振り返り、気づいてもらい行動を促します。
エネルギーかばんは、「省エネ」というキーワードを具現化したツールになりますが、他にも「地産地消」、「温暖化原因」、・・・といった各キーワード毎にツールがたくさんあります。

Q3:ツールはどのくらいあるのですか?
A:2011年6月現在で25程度あります。また、順次増やしています。
地球温暖化防止活動推進センターは各都道府県に存在しますが、その各センターを取りまとめている全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)というところが、主に温暖化防止に関係するツールを開発しています。

Q4:ツールを用いて、環境保全の普及啓発活動をする上での基本的なコツなど教えていただけますでしょうか?
A: まず、活動のパターンとして、出前講座をイメージしてください。
つまり、学校や企業に行って講座、もしくは受講生を募集して講座を開催というように、自分が講師で受講生が20〜30名程度いるパターンです。
「基本的なコツ」ということですので、細かいことは置いておくと、大きく3点あります。
【1】ツール自体をきちんと理解する
これは、当たり前ですが、自分がツールを完全に把握し扱えないと始まりません。
【2】講座の起承転結(ストーリーライン)を作り、リハーサルをする
ツールを理解し使えるようになることと、教えることとの間には大きな距離が存在します。
学校の試験問題を自分が解けても、友人に質問されて教える時、しゃべりがスムーズに行かなかった経験はありませんか?
これと同じパターンに陥らないように、事前にどのように進めるかの起承転結(ストーリーライン)を作り、リハーサルをし、できれば何も見なくても進められるようになればスムーズに講座ができます。
もちろん、起承転結(ストーリーライン)を作っても、その通りに進まないこともあると思いますが、基本は、作った起承転結(ストーリーライン)を柱として、(経験がいりますが)その場その場で柔軟にアドリブを組み込むことも重要になります。
【3】状況に応じてツールはアレンジする
ツールは、そのままでも完成度は高く仕上がっていますが、その場の状況でアレンジすることで効果が倍増します。
その場の状況とは、「参加者の人数・年齢」「参加者の知識レベル」「所要時間」「地域」などの要因が挙げられます。
高齢者向けの講座と小学生向けの講座では、同じツールを使用してもトークの内容などを変える必要があるのがイメージできると思います。
例えば、香川で実施する講座なら、名物うどん、慢性化する水不足など地域の特性を組み込んだ講座にした方が、受講者も興味深く聞いてくれます。

Q5:最後に、環境リーダー候補生に一言お願いします。
A:JCCCAのツールはどれも小学生から高齢者まで楽しみながら、エコを学べる、気づける、そして意識を高め行動を促すものとなっており、完成度の高いものばかりです。
ぜひこの機会に楽しみながら習得し、実際の活動の際に大いに活用いただきたいと思います
== 研修では、環境リーダーが、出前講座などの講座で広く活用できる活動ツールを伝授していただくことを期待しています。ありがとうございました。==