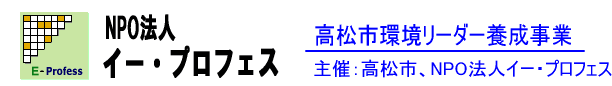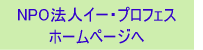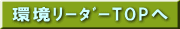※このページでは、講師や関係者に研修内容などについてインタビューした内容を掲載しています
エコ工作の講師担当のクラフト工房 オオニシ大西様に研修内容などについてお伺いしました。
エコ工作研修においては、環境リーダー候補生に、実際に工作教室を受講してもらうことで、来年度以降の活動に利用できる工作ネタの習得を目的としています。
講師プロフィール
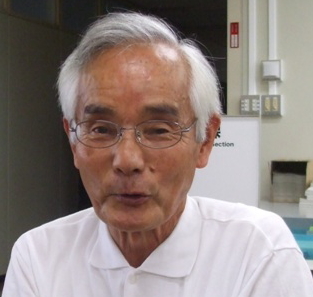
1943年、高松市生まれ。28年間、プラスティック成形業に勤務され
ましたが、2001年に健康を害し、第1線を退く。
その後は、子どもの健全育成に資するため、牛乳パックやペット
ボトルなどの身近な品々を活用して子どもたちの大好きなおもちゃ
などを工作する特技を生かして、生涯学習センターやコミュニティ
センター、保育園・幼稚園、各種イベントで各種の工作教室を開催。
2003年にクラフト工房オオニシをオープン。
子どもたちが休む、土曜日曜、夏休み等の期間中は、教室開催の
依頼が相継ぎ、引く手あまたの状況。作品のほとんどは氏が創作
によるオリジナル作品で、レパートリーは数え切れない。
また、バルーンアーティストとしても活躍中。
他に、高松市少年教育指導員、高松市レクリエーション協会理事、香川県子ども会活動指導員、あそびの城高松茜会館指導員などを務める。

Q1:実際の中身は当日までのお楽しみですが、今回のエコ工作研修ではどのようなコンセプトで工作ネタを選択される予定でしょうか?
A: 「環境リーダーが、実際の活動をする際に利用しやすいネタ」という一言に尽きると思います。
環境リーダー候補生の中には、工作や実験などを通して環境保全活動をバリバリやっている方もいるかと思います。一方で、これから環境保全活動しようという方もいると思います。
いろんな受講生がいる中で、教えるネタですので、「作り方が複雑でないもの・難しくないもの」が第一です。
次に、「小学生対象」です。実際、エコ工作教室という講座を開催した場合、子ども(特に小学生)がターゲットとなる場合が多いです。
環境リーダー候補生(つまり大人)が受講して面白いネタではなく、実際の活動の際のターゲットとなる小学生が喜ぶネタである必要があります。私は長年にわたり多数教室を開催していますので、どのようなネタがうけがよいか把握しています。

Q2:工作教室を実施する際のポイントなどはありますか?
A:「工作を教えて、自分で作れるようになる」というのは基本ですが、家庭教師のようなマンツーマンではないため、教室のマネジメントが重要となってきます。
特に小学生などの子どもたちは、集中力が途切れたり、飽きたりしないように進めていかないと収拾がつかなくなります。研修という意味では、このあたりのノウハウなども盗み取って欲しいと思います。

Q3:実際、年間どのくらい教室などを開催しているのですか?
A:ここ数年は年間300教室程度です。
土日はどこかしらで教室をしています。高松市教育委員会、生涯学習センターでは、2005年度から、毎月第1土曜日の午後、子ども向けの工作教室を開催しております。長年お付き合いさせていただき感謝しております。

Q4:何種類程度工作ネタをお持ちなのですか?
A:作品のほとんどが、私が創作したオリジナルで、使用する素材や素材の扱い方の組み合わせによって、まったく異なる作品が完成しますので、レパートリーは数え切れないほど多くあります。

Q5:工作に対するポリシーなどありますでしょうか?
A:まず、「同じ教室で同じネタは実施しない」です。
次に、「出し惜しみしない」です。
「自分で考えたネタ・ノウハウなので他人に使わせたくない」という野暮なことは言いません。普及目的でやっていますので、ドンドン盗んで使っていただいて結構です。
また、前述の通り毎回違うネタでやる方針なので、盗まれても私もドンドン開発・創造していきます。ネタが尽きることはありません。

Q6:研修とは少しそれますが、工作教室活動を始められたきっかけをお話し願えないでしょうか?
A:子どもが好きで、子ども達の健全育成に少しでも役に立ちたいという思いが第1です。幸いにも、現役時代に、大量生産ではなく、少量のものを手作りで生産するものづくり業に従事していましたので、様々な素材や道具の使い方などの知識を有していましたので、これが役立っていると思います。
== 研修では、2011年度に環境リーダーが、出前講座などの講座で広く活用できる工作ネタを伝授していただくことを期待しています。ありがとうございました。==